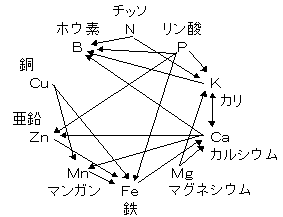 肥料要素の間には、互いに植物への吸収を妨げあう作用があり、この作用を拮抗(きっこう)作用と呼ぶ。例に挙げると、チッソ(N)→ホウ素(B)はチッソが多すぎると、土の中にホウ素が十分あっても、植物はホウ素を吸収できない。
肥料要素の間には、互いに植物への吸収を妨げあう作用があり、この作用を拮抗(きっこう)作用と呼ぶ。例に挙げると、チッソ(N)→ホウ素(B)はチッソが多すぎると、土の中にホウ素が十分あっても、植物はホウ素を吸収できない。
BOD
(びーおーでぃー)
生物化学的酸素要求量のこと。水質汚濁の指標の1つ。水中の微生物の増殖・呼吸によって消費される酸素量のこと。
CA貯蔵
(しーえーちょぞう)
貯蔵庫内の温度を下げ、あわせてガス濃度を調節することにより、果実の呼吸作用を抑制し、貯蔵性を高める方法。酸素濃度を減らし、炭酸ガス濃度を上げることが一般的だが、その割合は果実の種類によって異なる。 リンゴなどの貯蔵法。COD (しーおーでぃー)
化学的酸素要求量のこと。水質汚濁の指標の1つ。
IPM
(アイピーエム)
総合的害虫管理の略。化学合成農薬だけを用いて害虫を防除するのではなく、天敵などのあらゆる適切な技術を活用して、害虫個体数を低いレベルに維持・管理しようとする防除体系。
LC50
(えるしーごじゅう)
一定の条件下で薬物を接触させたり,投与し,その動植物の50%が死ぬ濃度のこと。LD50 (えるでぃーごじゅう)
急性毒性半数致死量のことで、試験動物の半数を2日以内に死なせる投与量(mg)をその動物の体重(kg)で割った数値。数値が低い方がより急性毒性が高いこととなる。当然人間で行うわけにはいかないのでラットやマウスを使用するため、その数値が直接人間に当てはまるかは分からないので農薬の登録にはその観点も考慮し厳しいものとなっている。
MA包装
(えむえいほうそう)
見た目は普通のビニール袋だが、ミクロ単位の穴が空いていて、酸素と二酸化炭素をコントロールし鮮度保持の包装方法。
pH
(ぺーはー)
土の酸性度のこと。植物の生育は多くの場合pH5〜6の弱酸性が適正であるが、日本の土壌は4〜5の場合が多く、アルカリ性の資材をやる必要がある。石灰資材(pH=11)や堆肥(pH=8)をやると良い。
亜主枝
(あしゅし)
主枝から分岐した枝で側枝、結果枝などを着け、主枝と同様に樹形の骨組みとなる枝。アブシジン酸 (あぶしじんさん)
→骨格枝
植物ホルモンの1つで,作用として,落葉などの脱離誘導,休眠誘導,種子発芽抑制,気孔の開閉調節による水不足の対応などがり,ミヨビという肥料にはアブシジン酸が含まれており,農業利用されている。アレロパシー (あれろぱしー)
→植物ホルモン
1つの生物や植物が離れている他種の生物や植物に影響を与える現象。例えばある種の植物が生えていることが,雑草を抑制したりする現象のこと。1年生枝 (いちねんせいし)
その年に伸びた枝。2番伸びがなければ1本の棒状である。市場外流通 (いちばがいりゅうつう)
産地と消費地との直接取引で卸売市場を経由しない流通方式。系統出荷でも市場を通さないものは市場外流通となる。いや地 (いやち)
土壌に起因するなんらかの生育障害のこと。連作障害のことを指すこともある。果樹ではモモのプルナシンなどが知られている。ウイルス (ういるす)
細菌よりもさらに小さく,生きた細胞のみで増殖する微生物。モザイク病などの原因となるもの。ウイルスフリー (ういるすふりー)
ウイルスに犯されていない植物のこと。ウイルスは原則的に種子伝染しないので,世代更新によって無ウイルス化できるし,栄養繁殖性植物は茎の生長点から植物を再生することによって無ウイルス化できる。腋花芽 (えきかが)
→茎頂培養
1年生枝の葉の根本に着く花芽。エチレン (えちれん)
植物ホルモンの1つで,気体のホルモンです。作用として,発芽,開花,果実の成熟,落葉などの脱離,老化の促進と細胞分裂阻害,伸長成長阻害(一部の植物では成長促進)があります。園芸療法 (えんげいりょうほう)
エスレルという名で販売されています。
→植物ホルモン
共同作業で草花を育てることで、コミュニケーションが芽生え,手先を動かすことで農を活性化させるメリットがる。高齢者や身体障害者が良く行っている。エンゲル係数 (えんげるけいすう)
家計費に占める飲食費の割合。ドイツの社会統計学者エンゲルが「労働者の所得が増加するにしたがい、飲食費の支出割合は絶えず減少する」法則を発見し、発見者の名前からこう呼ばれる。オーキシン (おーきしん)
最初に発見された植物ホルモンで,作用として,茎・根の伸長成長,頂芽の成長,果実の肥大,発根,組織分化などの促進,側芽の成長,果実,葉の脱離などを阻害します。
なお,天然のオーキシンは植物体内で不安定であり,また自然界では用意に分解するため,農業上利用はできません。安定的な合成オーキシンが利用されています。トマトトーン,フィガロん乳剤など。
→植物ホルモン
カイロモン
(かいろもん)
異種生物間に作用する「他感物質」の1つ。受け手に適応的に有利に作用するが,放出者にはそうでないもの。例えば,寄生蜂の寄主が放出する物質のこと。化学肥料 (かがくひりょう)
化学的手法により工場などで製造される肥料。過リン酸石灰,石灰窒素などがある。言葉の使用方法として,天然の動植物質有機肥料に対して使用する場合が多い。隔年結果 (かくねんけっか)
結実の多い年と、結実が少ないか、ほとんどない年とが1年おきに続く現象。養分が果実にとられて、次の年の花芽に養分が行き渡らないため起こる。加工尿素肥料 (かこうにょうそひりょう)
IB(イソブチルアルデヒド加工尿素肥料)、CDU(アセトアルデヒド加工尿素肥料)、UF(ホルムアルデヒド加工尿素肥料)などで、これらの表記があれば、徐々に硝酸態やアンモニア態の窒素になる肥料を指す。化成肥料 (かせいひりょう)
肥料の製造工程で化学的操作を行う肥料。粒状肥料などはすべて化成肥料。可溶性 (かようせい)
クエン酸アンモニウムアルカリ溶液に溶けるものカルス (かるす)
→水溶性 、 く溶性
植物に傷を付けたときに,その周辺にできる治癒組織のこと。緩効性肥料 (かんこうせいひりょう)
肥料成分が長期にわたって溶け出し,肥料効果が持続する肥料完全渋柿 (かんぜんしぶがき)
受粉してもしなくても渋柿になる品種。これに対して受粉してもしなくても甘柿になる品種を完全甘柿、受粉しなければ甘柿にならない品種を不完全甘柿という。一般に受粉すると種のあるカキになる。間伐 (かんばつ)
樹同士の間隔を保つために、樹を根本から間引くこと。帰化植物 (きかしょくぶつ)
新たな生育地で生活ができるようになった植物。セイタカアワダチソウ,セイヨウタンポポなどが日本で生育しているのが代表例。拮抗作用 (きっこうさよう)
基部優性 (きぶゆうせい)肥料要素の間には、互いに植物への吸収を妨げあう作用があり、この作用を拮抗(きっこう)作用と呼ぶ。例に挙げると、チッソ(N)→ホウ素(B)はチッソが多すぎると、土の中にホウ素が十分あっても、植物はホウ素を吸収できない。
樹冠の内部が外側より、徒長枝など太く長い新梢が出やすい現象。菌類 (きんるい)
主として,かび,きのこ,酵母類の総称。細菌類を含める場合もある。く溶性 (くようせい)
2%クエン酸液に溶けるもの車枝 (くるまえだ)
→水溶性 、 可溶性
同じ個所から3本以上の枝が出ている状態茎頂培養 (けいちょうばいよう)
生長点(茎頂分裂組織)を切り出し培養し植物体を再生させる方法。生長点は細胞分裂が活発でウイルスがほとんどないため,ウイルスフリー植物を作る目的で用いる方法。系統出荷 (けいとうしゅっか)
→ウイルスフリー
青果物の生産農家が農協組織を通じて出荷すること。結果枝 (けっかし)
花芽を着けて翌年開花結実する枝の総称。長さによって名称が異なり、目安として10cm以下を短果枝、10〜30cmを中果枝、30〜50cmを長果枝と呼ぶ。結果母枝 (けっかぼし)
結果枝を出し、結果枝に、花をつけ、果実をつける枝。ぶどう、かんきつ類、かき、くり、キウイなどにある。光合成 (こうごうせい)
光合成は、炭素同化作用、炭酸同化作用あるいは簡単に同化作用とも呼ばれ、緑色植物が光のエネルギーを利用して、炭酸ガスと水から糖やデンプンなどのような炭水化物を合成する働きをいう。交雑 (こうざつ)
遺伝子型の異なる系統,異品種,異種,異属間で行われる交配のこと。植物では品種改良のために行われる。耕種的防除 (こうしゅてきぼうじょ)
病害虫の防除を農薬にたよらず,土壌改良,耕起,輪作などの栽培方法の改善により防除を行う方法。耕起 (こうど)
耕土をすき起こし、表層部の土壌と深層部の土壌を反転させる作業。骨格枝 (こっかくし)
主枝と亜主枝のこと。根域制限栽培 (こんいきせいげんさいばい)
→主枝、 亜主枝
大きくなる果樹は管理が難しいため、根の伸びを制限し樹型をコンパクトにする栽培方法。植木鉢に植えるのもその1つの方法。コンパニオン・プランツ (こんぱにおん・ぷらんつ)
共栄作物ともいい,ある種の植物どうしをうまく組み合わせて、病害虫や雑草の被害をなくしたり減らすことができる相性のよい植物のことコンポスト (こんぽすと)
ゴミや汚泥等を比較的短時間(1週間程度)に発酵させて衛生処理された人工的堆肥すること。混芽 (こんめ)
花のもとと葉のもとの両方をもっている芽。結果母枝に着いている花芽のこと。根粒菌 (こんりゅうきん)
豆類の根に共生する細菌。窒素固定能力の高い菌を用いて窒素施用量を節減する。
細菌
(さいきん)
単細胞で堅い細胞壁を持つ微生物。土壌微生物中最も小さい。サイトカイニン (さいとかいにん)
植物を切断すると,切り口を治癒する細胞塊(カルス)が作られることをヒントに発見された植物ホルモンで,サイトカイニンとは,細胞分裂を促進する化合物の総称です。三相分布 (さんそうぶんぷ)
作用として,カルスの形成,側芽の成長,細胞の拡大,クロロフィル合成促進,種子発芽の促進があります。フルメット液剤などが利用されています。
→植物ホルモン
土壌の気体部分(気相),液体部分(液相),固体部分(固相)のバランスのこと。有機物が少ないなどの原因により,気相が減るなどバランスが悪くなる。雑種 (ざっしゅ)
→単粒構造、 団粒構造
ハイブリッドともいい,遺伝子形質の異なる個体間の交雑で生じた子孫のこと。施設栽培 (しせつさいばい)
一般の露地栽培に対し,温室,ハウスなどの施設を使った集約栽培のこと。集団転作 (しゅうだんてんさく)
緊急生産調整推進対策に係る水田転作で,地縁的に団地を形成し,地域ぐるみで行っているものをいう。主幹 (しゅかん)
地上から最上位の主枝の分岐点までの幹の部分。主業農家 (しゅぎょうのうか)
→主枝
農業所得が主(農家所得の半分以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家縮伐 (しゅくばつ)
→副業的農家
樹同士の間隔を保つために、枝葉を切りつめること。主枝 (しゅし)
主幹から直接分かれて出た枝で、亜主枝、側枝、結果枝などを着け樹形の基礎となる枝。3本あれば3本主枝と呼ぶ。雌雄異花 (しゆういか)
→主幹、 骨格枝
1つの花の中に,雄しべか雌しべのどちらか1つしかないか,あっても退化している花。果樹ではカキ,キウイ,銀杏など。雌雄同花 (しゆうどうか)
1つの花の中に雄しべと雌しべ,両方とも持つ花。果樹ではリンゴ,ナシ,モモ,ウメ,ブルーベリーなど多数。植物ホルモン (しょくぶつほるもん)
オーキシン,ジベレリンなどで,植物体の中で生産され,微量で何らかの生長に影響をおよぼすもの,のこと。植物連鎖 (しょくもつれんさ)
→サイトカイニン、 ブラシノステロイド、 アブシジン酸、 エチレン、 オーキシン、 ジベレリン
植物プランクトン→動物性プランクトン→小魚→大魚→人間というように,植物エネルギーなどが高い栄養段階に移ること。最近ではこの流れが複雑化し,植物連網(food web)と呼ばれる。脂溶性 (しようせい)
油溶性ともいい、油に溶けること。水溶性の逆。芯腐れ (しんぐされ)
リンゴ、ナシなどの果心部(種のある部分)が収穫期に褐変する症状。果実の熟しすぎや病原菌による腐敗などが原因とされている。新梢 (しんしょう)
新しく生長している、葉を着けている1年生枝。伸び方によって発育枝、結果母枝、徒長枝などとなる。ジベレリン (じべれりん)
日本人が稲の馬鹿苗病から発見した植物ホルモンで,この病気の病原菌が出す毒素が馬鹿苗(徒長苗)にしていることから,この毒素が単離されました。この物質は馬鹿苗病菌の学名(Gibberella fujikuroi)からジベレリンと命名されました。準主業農家 (じゅんしゅぎょうのうか)
その後,ジベレリンと同じ作用を持つ物質が植物体に含まれていることが分かり,現在80種類以上が発見されています。これらは,発見された順番にジベレリンA1(GA1)と番号がついています。市販のジベレリンはGA3。
作用として,茎,根を細長く伸ばすのが主な特徴です。他にも抽だいの誘導,春化処理の代用,発芽促進,開花促進,勝つ実促進,落葉抑制などがあります。
→植物ホルモン
農業所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家純水 (じゅんすい)
→副業的農家
読んで字のごとく、「不純物を含まない水」という意味です。水をイオン交換樹脂に通過させ作るため、イオンがとりのぞかれた水です。常葉果樹 (じょうりょくさいばい )
1年中、落葉しない果樹のこと。ミカン、ビワなど。植え付けは3月頃に行う。人工授粉 (じんこうじゅふん)
→落葉果樹
りんご、なしなどで花粉を採種し、人工的に雌しべに付着させ、受精を行わせること。水溶性 (すいようせい)
水に溶けるもの整枝 (せいし)
→く溶性 、 可溶性
枝の数を適当に制限したり、またその配置を図って作柄をよくすることを整枝という。生分解性 (せいぶんかいせい)
→芽かき
単純な生化学的素材や科学的素材に生物学的な分解を受けること。自然界で分解するマルチやテープナーテープなどがある。生理障害 (せいりしょうがい)
細菌,ウイルス,その他病原性微生物や害虫によるものでない障害。植物の生育環境などが原因で植物体に生理的・形態的異常が生じること。生理的落果 (せいりてきらっか)
果実の発育途中に暴風雨、病害、薬害以外の原因により落果すること。専業農家 (せんぎょうのうか)
世帯員のうち兼業従事者が1人もいない農家選択性農薬 (せんたくせいのうやく)
特定の害虫のみに高い毒性を持つ農薬のこと。つまり,人に対する毒性は低く,人に対する安全性は高いとされる。せん定 (せんてい)
枝を切ること。伸びた枝の途中から切ることを「切り戻しせん定」、枝の根本から切ることを「間引きせん定」という。総合的害虫管理 (そうごうてきがいちゅうかんり)
化学合成農薬だけを用いて害虫を防除するのではなく、天敵類などあらゆる適切な技術を活用して害虫数を少ない状態で維持・管理しようとする防除体系。IPM(Integrated Pest Management)とも呼ばれている。側枝 (そくし)
結果枝や結果母枝を着ける枝。促成栽培 (そくせいさいばい)
加温などをして,人工的に作期を早めること。組織培養 (そしきばいよう)
植物体の一部から無菌的に培養すること。一部とは茎、葉、根、花器、果実などの細胞のこと。速効性肥料 (そっこうせいひりょう)
肥料をやるとすぐに根から吸収されて,植物体に吸い上げられる肥料。主に追肥に使われる。
耐寒性
(たいかんせい)
低温によく耐える性質。対抗植物 (たいこうしょくぶつ)
キタネグサレセンチュウ、サツマイモネコブセンチュウなどを効果的に減少させる植物で、代表的なものにマリーゴールドやラッカセイがある。耐暑性 (たいしょせい)
高温によく耐える性質耐性 (たいせい)
従来作用していた農薬(殺菌剤等)が,その細胞や微生物などに対し効果がなくなること。堆肥 (たいひ)
有機物を原料とし、好気的発酵によって腐熟させ、成分的に安定化したもの。わら、落ち葉などを発酵させたものを堆肥、家畜糞尿を主原料とするものをきゅう肥と区別していたが、1本化し堆肥と呼んでいる。耐病性 (たいびょうせい)
植物がどれだけ病気にかかりにくい性質かということ高接ぎ (たかつぎ)
接ぎ木の1種で,果樹で品種更新を行う際に,枝の上部(高い位置)で接ぎ木をする方法。多年草 (たねんそう)
→接ぎ木
長年にわたって生育し、開花結実する草本植物をいう。球根類も広義では多年草に属するが、一応含めない。単為結果 (たんいけっか)
受粉、受精しないで果実を形成する現象。 単位結果する果樹は渋柿,温州みかん,イチジクなど。短果枝 (たんかし)
10cm以下の枝。短果枝に着生する花芽を短果枝花芽と呼ぶが、略して短果枝を呼ぶことが多い。単粒構造 (たんりゅうこうぞう)
→中果枝、 長果枝
土の粒子が1つ1つそのままの状態で重なっている状態。有機物などが足りない状態で,気相も少ない。台木 (だいき)
→三相分布
果樹栽培では、生育の強さの調節、病害虫に対する抵抗力の増強、結実までの期間短縮などの理由から接ぎ木苗が使われる。この接ぎ木を行う根の方の部分を台木と呼ぶ。団粒構造 (だんりゅうこうぞう)
→接ぎ木、 穂木、 接ぎ木親和性
土壌の粒子のいくつかがくっついて塊をつくり,その塊が粗密に並んだ土壌。気相,液相のバランスが良く,作物を作るのに適している。中果枝 (ちゅうかし)
→三相分布
10〜20cmの新梢。長果枝 (ちょうかし)
→短果枝、 長果枝
30cm以上の新梢。徒長枝、発育枝も長果枝の1つ。頂花芽 (ちょうがめ)
→中果枝、 短果枝
花芽の中で枝の1番先に着く花芽。頂部優性 (ちょうぶゆうせい)
立ち枝では上の芽から出た新梢のほうが太く長くなる現象。地力 (ちりょく)
土地が作物を生育させることのできる能力、土地の生産力のこと接ぎ木 (つぎき)
地下部(根)と地上部(枝葉)で異なる品種を利用する場合に枝と枝をつなぐ方法。野菜などでは土壌病害に強い品種を根においしい品種を接いだりする。接ぎ木親和性 (つぎきしんわせい)
→台木、 接ぎ木親和性、 高接ぎ
接ぎ穂と台木が完全に活着し、順調に生育する場合をその接ぎ穂と台木に親和性があるという。親和性が悪いと発育が悪くなったりする。活着が良くても、数年間生育した後で実の成りが悪いなど長期的に親和性がよいものを接ぐ必要がある。土づくり (つちづくり)
→接ぎ木、 台木
土壌の物理性、化学性、生物性を改良することにより、土壌の作物生産能力を向上・保全すること。低温耐性 (ていおんたいせい)
低温によく耐える性質低温貯蔵 (ていおんちょぞう)
貯蔵庫内の温度を果実貯蔵の最適温度まで下げて貯蔵する方法。低温要求 (ていおんようきゅう)
芽や種子は春先の高温によって発芽するが、その前に低温を必要とする現象。樹種によって要求する温度と時間は異なる。抵抗性 (ていこうせい)
従来作用していた農薬(殺虫剤等)が,その生物(害虫や線虫など)に対し効果がなくなること。また,品種改良時にある種の病気に強い品種を作ること(○○病に対して抵抗性のある品種とか言う)。摘心 (てきしん)
枝分かれのため,草丈を調整するために,枝先の芽をつみ取ること。以前の漢字は摘芯。摘果 (てっか)
リンゴ、ナシ、カキ、ブドウなど多くの果樹では、果実を大きく、品質の揃ったものにするため、蕾(つぼみ)や幼果の時につみ取って、最終的な果実数を制限する栽培方法。転作 (てんさく)
米の消費減少により水田(田んぼ)に米以外の作物を作ること。展着剤 (てんちゃくざい)
農薬などを散布するときに,薬剤が水に溶けて植物や病害虫に付着して,効力を増加,持続するように混ぜる補助的薬剤。農薬取締法上は農薬。天敵 (てんてき)
害虫を侵す自然界の外敵を天敵という。天敵を保護・増殖させると害虫の被害を軽減させることができる。徒長枝 (とちょうし)
発育枝の中でも枝の直上などから発生した非常に強勢で長い新梢。土壌改良資材 (どじょうかいりょうしざい)
土壌の物理・化学・生物的性質を改善するもの。地力増進法では「肥料にあっては,土壌に化学的以外の変化をあわせてもたらすことを目的として土地に施用させるもの」と定義されている。
ネクター
(ねくたー)
完熟した果実を粉砕し、裏ごししたピューレを水で希釈した果肉飲料。ペクチンなどパルプ質が多く含まれるため粘着性がある。農用地区域 (のうぎょうちくいき)
農業振興地域のうち農用地として利用されるべき土地の区域で、農業目的以外の土地利用の規制されている。農薬 (のうやく)
農産物等の生産・品質に悪影響を及ぼす害虫、病気、雑草などの駆除、防除を行うための薬剤。農薬取締法では生物農薬、フェロモン剤、植物成長調製剤(ホルモン剤)なども農薬としている。
発育枝
(はついくし)
葉芽のみを着けた1年生枝だが、多くの場合、花芽を着けた1年生枝でほど良い長さ・太さの枝を指す。次年度の側枝、予備枝となり得る枝。花芽 (はなめ)
翌年咲く花のもとをもっている芽。葉芽 (はめ)
翌年に生長する枝葉のもとだけをもっている芽。バイオマスエネルギー (ばいおますえねるぎー)
風力、太陽電池などなど再生可能なエネルギー(renewable energy)の1つで、植物の力によるエネルギーのこと。有名なところではサトウキビの糖からエタノールを生成し、車の燃料としている、ブラジルの例がある。パーライト (ぱーらいと)
真珠石や黒曜石を高温焼成したもの。通気性と排水性に富み,土壌改良剤に利用される。肥効 (ひこう)
肥料を施したことによる効果をいう。ひこばえ (ひこばえ)
樹木の切り株や根元から群がり生える若芽。いらない枝なのですべて切り取る。被覆肥料 (ひふくひりょう)
被覆、ロング、LPなどの言葉が表記してある肥料のこと。コーティング肥料ともいい、カプセル状の膜の中に肥料が入れてあり、徐々に溶け出す肥料。肥沃土 (ひよくど)
土(土地)が肥えて、作物の生育に適する土壌のこと品種 (ひんしゅ)
同じ品目で、異なる種類のことを指す。ブドウでいうとデラウエア,巨峰,ナシでいうと幸水,二十世紀、リンゴでいうとふじ、王林、紅玉を指す。品目 (ひんもく)
野菜の種類や、果樹の樹種のこと。水稲、トマト、キュウリ、りんご、ナシなどのこと。微生物農薬 (びせいぶつのうやく)
微生物そのものあるいは微生物の抽出物を有効成分とする病害虫防除資材。ピートモス (ぴーともす)
寒冷な湿潤地のミズゴケ類が堆積,分解してできた有機物。保水性に富み,土壌改良剤に利用される。pH未調整でpH4程度と低く,低pHを好むブルーベリーの有機物補給として利用される。フェロモン (ふぇろもん)
生物(主に動物,昆虫)が体外に分泌し,同種の個体間で作用する物質。代表例は雌の昆虫が雄を引き寄せるために分泌する(カメムシなど)。富栄養化 (ふえいようか)
湖沼などに窒素,リンなどが流入し,水中におけるそれらの濃度が高まる現象のこと。副業的農家 (ふくぎょうてきのうか)
主業、準主業農家以外の農家袋かけ (ふくろかけ)
→主業農家 、 準主業農家
病気の侵入を押さえるため、果実を直接袋で覆う方法。 ブドウやモモで行われる。腐植 (ふしょく)
酸素の乏しい土壌中で,細菌などの作用で植物が不完全に分解すること。腐葉土 (ふようど)
広葉樹が落葉,堆積して土状になったもの。保水性,保肥性,通気性,排水性に優れる。不和合性 (ふわごうせい)
自家受粉や、ある系統間の交雑では生理的に不稔になること。ブラシノステロイド (ぶらしのすてろいど)
作用として,他の植物ホルモンを類似したものも多く,茎などの伸長,葉の拡大,根の伸長など植物全体を大きくする。さらに老化の促進,温度ストレス,化学薬剤の薬害,塩害に強くなるなどがある。訪花昆虫 (ほうかこんちゅう)
→植物ホルモン
受粉が必要な植物の着果には花粉を運ぶ昆虫が必要で,この昆虫(ミツバチやマルハナバチなど)のことを指す。穂木 (ほぎ)
接木(つぎき)の台(台木)につぐ芽のことをいいます。ポスト・ハーベスト (ぽすとはーべすと)
→台木
農産物の輸入に伴う海外からの病害虫の侵入を防止したり、農産物の品質を保持する目的で、収穫後の農産物に農薬を使用すること。
マルチング
(まるちんぐ)
単にマルチともいい,土壌の乾燥防止,浸食防止,地温の調節,雑草防除などを目的に,資材により土壌表面を被覆することで,稲わら,麦わら,ビニール,プラスチックフィルムが用いられる。実生 (みしょう)
種子からその発芽によって育った植物のこと。芽かき (めかき)
余分に出た芽を若いうちに摘み取って、樹形を整えたり、果実・花の生育を調節すること。木酢液 (もくさくえき)
→整枝
材木などを蒸焼きにするとでてくる液体のことで,pH2〜3,酢酸含量3〜7%,その他有機化合物10〜20%を含み,植物の生長を促進あるいは阻害し,殺虫,殺菌効果もあるといわれている。元肥 (もとごえ)
作物を栽培する前にあらかじめ田畑に施しておく肥料。
薬害
(やくがい)
農薬や肥料を施用したために作物が被害にあうこと。例えば害虫を殺すために農薬をまいたところ,葉が落ちてしまったような場合。誘引 (ゆういん)
トマト・キュウリなど蔓性の野菜はもちろん、果樹でもナシやブドウなど棚栽培のものなどを,支柱や棚にひもなどでくくること。この作業を誘引という。有機質肥料 (ゆうきしつひりょう)
魚肥類、骨粉類、草木性植物油かす類等の動植物物質の肥料をのこと。生わら、堆肥等の土壌改良が主目的の粗大有機物の含めることがある。有機物 (ゆうきぶつ)
化学的には炭素(C)を含むもののこと。農業では有機栽培の言葉が先行し、自然物から産出したものが一般的解釈となっている。幼若性 (ようじゃくせい)
果樹でまだ木が若い時,果実が本来の品種特性でなく,味や大きさが異なる現象。幼樹開花 (ようじゅかいか)
グレープフルーツ等で播種1年で開花する現象。その後は幼若期となり数年は開花しない。葉面散布 (ようめんさんぷ)
植物は葉からも養分を吸収しうることを利用して,養液を葉に散布すること。葉緑素 (ようりょくそ)
クロロフィルともいい、緑色の色素。植物の葉やキュウリの実の色は葉緑素で緑色になっている。予備枝 (よびし)
次年度あるいはさらに翌年の結果枝を作るためにせん定した新梢。人工的に作られた枝を指す。ナシの二十世紀では待ち枝と呼ばれる。
落葉果樹
(らくようかじゅ)
秋になると落葉する果樹のこと。リンゴ、ナシ、カキ、ウメなどがある。植え付けは11月頃に行う。両全花 (りょうぜんか)
→常葉果樹
1つの花に十分にその機能をはたすことができる雄しべ、雌しべを備えている花のこと。緑肥作物 (りょくひさくもつ)
れんげやソルゴーなど肥料養分があり,栽培後に土壌に混ぜて,その後に作付けされる作物の肥料分となる作物のこと。
わい化栽培
(わいかさいばい)
植物体の成長を抑制し、樹形をコンパクトに抑える栽培法。わい性台木を用いる栽培はリンゴなどで一般的である。根域制限栽培もこの1つ。